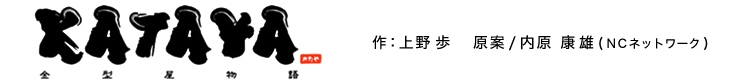

「そうですか、花丘製作所さん、代替わりされたんですか」
銀行の担当者が言った。
「ええ、それでご挨拶をと思いまして」
明希子は言った。
担当者の男性は三十代半ばくらいといったところだろうか、しばらく興味深げに明希子のことを眺めていた。
「いくらご実家の会社とはいえ、いまのような状況で継がれるなんて、勇気がある方だなあ」
こうした言葉にはとっくに慣れっこになっていた。
上席に引き合わせると言われ、菅沼と明希子は応接室に案内された。
しばらくして、髪をきれいに撫でつけた金縁眼鏡をかけた上品そうな風貌の上席が入ってきた。そうして、
「やあ、社長」
と、その見かけとは裏腹な横柄な感じで菅沼に声をかけた。
菅沼は一瞬ぽかんとしていたが、あわてて明希子のほうを示した。
「いえ、社長はこちらです」
こんどは上席のほうが唖然としていた。それから苦笑いを浮かべ、
「またまたあ」
「いや、ほんとうです」
そう言う菅沼を相手にせず、
「忙しいんだから冗談はよしましょうよ」
そう言って不愉快そうにソファにどかりと腰を下ろすと煙草に火をつけた。
明希子は刷り上ったばかりの名刺を差し出して、
「このたび株式会社花丘製作所の代表取締役に就任いたしました花丘明希子です」
「あっそー」
明希子が社長だとわかると、ますます気分を害したようだった。明希子の名刺の端を指でぱちぱちはじきながら言った。
「あんた、社長だなんていって、ほんとのところ名目だけなんでしょ? 後ろ盾になるひとの名前と経歴を書面で出してよ」
「そんなひとはいません」
「じゃあ、話にならないなあ。どうせ、融資の件できたんでしょ。まあ、お宅のメインバンクにでもお願いしたら」
「メインバンクは貴行です」
――話にならないのはどっちだ!自分の銀行の古くからの取引先も知らないなんて!!
「まったくひでえ態度だったなあ。いくら、いまがこんなだからって。いや、長いこと優良企業だったんですよ、うちは」
銀行をあとにすると菅沼が言った。
「ま、雨が降った時には傘を貸さない、晴れてる時は傘を貸す――それが銀行ってもんだっていいまさあね」
「いまに言わせてみせるわ、向こうのほうから“借りてください!”って」
明希子は言った。
「そう!その意気ですよ、アッコさん」
会社にもどると、ふたたび高柳の部屋のまえを通りかかり、明希子は立ち止まった。
EMIDAS magazine Vol.16 2007 掲載
※ この作品はフィクションであり、登場する人物、機関、団体等は、実在のものとは関係ありません