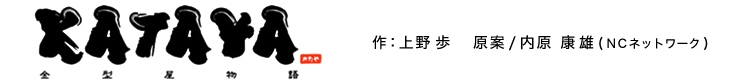

「おはよう」
と明希子は挨拶した。
すると、仙田がぷいと顔をそむけた。
仙田は、製造部で葛原とならぶベテランの職人である。
明希子は仙田を追うようにしてもういちど声をかけた。
「おはよう」
だが、仙田のほうは相変わらず無視している。いつものことだった。
社長になって当面なにをしていいものか明希子にはわからなかった。そこでひとまず社員とふれあおうと思い、全員に声をかけることにした。「お疲れさま」とか「元気?」とか、一言でいいから、毎日ひとりひとりに話しかけた。でも、なかには、けっしてこたえてくれない社員もいた。仙田もそうだった。
きょうはかならず挨拶を返してもらうぞ、と意気込んで、仙田のまえに明希子は立った。
「おはよう!」
すると、仙田が無言のまま明希子をまじまじと見返してきた。
明希子も仙田の顔を正面から見据えた。しゃくれた顎に無精ひげがまばらにのびている。そこに白が多く混じっていた。
やがて仙田がまたそっぽを向いた。
明希子はその視線の先に立って、さらに言う。
「お・は・よ・う」
こんどは仙田が下を向いた。明希子はからだを傾けて、その顔を覗き込んだ。
「仙田さん、おはよう」
明希子はにんまり笑った。
「けっ、しつけぇなあ」
仙田がぼそりと言った。だがそのあとで、むすっとした表情がほどけ、にやりと微笑んだ。
「おはようさん。これでいいんだろ」
そう言うと、仙田はすたすたと去っていった。
明希子はその後ろ姿を見送りつつ、
――ま、一歩前進てとこね。
と思う。
「お嬢、すいやせんねえ」
葛原だった。横から見ていたらしい。
「なにしろセンさんは一途な男でね。やつには、社長っていったら先代しか、お嬢のお父さんしかいねえんですよ。いや、悪く思わないでくだせえ」
――「花丘製作所の社員にとって社長はただひとり、あなたのお父さんだ」落合の言葉が明希子のなかでよみがえる。
「夏の暑い日にね――いや、昔のことでさあ」
葛原が遠い眼をした。
「先代が“がんばれ”って、現場の人間ひとりひとりに栄養ドリンクを配ってくれたことがあったっけ。当時はね、まだ高かったんじゃねえかなあ、ああいうの。それからクリスマスに、きょうは寄り道しないでまっすぐ帰れよって、ケーキ持たせてくれたりね。そういうことをひとつひとつおぼえてんだな、おれもセンさんも、いや、みんながさ」
明希子は黙って聞いていた。